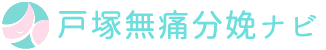Article早産はいつから?早産の兆候や気をつけたい症状、対策について解説
コラム 2025.02.23

妊娠や出産にはさまざまなリスクがありますが、なかでも心配という声が多いのが「早産」です。「いつからが早産になるのか」「自分は早産になりやすいのか」気になる方も多いと思います。
過去に早産の経験がある、子宮の病気や妊娠糖尿病などの病気がある場合は早産を起こしやすくなります。しかし、早産はこれらの原因がなくても誰にでも起こる可能性があります。本記事では、早産と言われる時期や、原因について解説します。病院に相談をした方が良い兆候や対策についても紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
いつから早産になる?
赤ちゃんが生まれてくるのに適した時期は妊娠37週0日〜41週6日までで、この時期に生まれてくることを「正期産」と言います。それより早い妊娠22週0日から妊娠41週6日の出産は「早産」と定義されています。妊娠22週未満に生まれてしまった場合は、赤ちゃんが生きるのが難しいとされており、「流産」にあたります。
早産は、日本産婦人科学会によると妊娠全体の約5%程度あります。早産で生まれると、病気になりやすくなることや、重篤な障害が起こる可能性があります。また早産になりそうな状態のことを「切迫早産」といいます。切迫早産と診断された方のうち早産になる確率は30%程度と言われています。
自然早産と人工早産ってなに?
早産には、「自然早産」と「人工早産」があります。子宮や胎児の状態などにより、未熟な状態の赤ちゃんを子宮内にとどめておくことができず、早く生まれてきてしまうことを「自然早産」と呼びます。自然早産は、早産全体の75%程度にあたります。
一方、胎児や母体の健康状態が思わしくなく妊娠を継続できない場合は、帝王切開や誘発分娩により人工的に出産を進める「人工早産」を行うことがあります。胎盤の異常や妊娠高血圧症候群などの合併症が重篤な場合などに行われます。
早産になりやすい人や病気は?
早産になりやすい人や妊娠の状態、病気は以下の通りです。
・過去に早産の経験がある
・妊婦が18歳未満や35歳以上の場合
・子宮の病気や治療の経験がある
・膣や子宮の感染症を起こしている
・妊娠糖尿病や妊娠高血圧がある
・双子以上の多胎妊娠
過去に早産した回数が多い、またその時期が早いほど再発のリスクが高くなり、自然早産を繰り返す確率は20%程度あると言われています。また、胎盤が剥がれる「常位胎盤剥離」などの胎盤の異常があると胎児が危険な状態になるため、それ以上妊娠を継続できず、人工的に出産させます。
子宮の病気や妊娠糖尿病などの合併症、多胎妊娠については詳しく解説します。
子宮の病気や治療の経験がある
通常、出産までは子宮頸管は硬く閉じられていて赤ちゃんが出てこないようになっています。一般的な子宮頸管の長さは35mm〜45mmほどあり、出産時には赤ちゃんが出てきやすくなるように柔らかくなりますが、それまでは赤ちゃんを子宮にとどめておく役割を果たしています。
しかし、子宮頸がんの治療で子宮頸管を切除した場合などは子宮頸管が短い場合や、ゆるくなっている「子宮頸管無力症」になることもあり、早産になりやすくなります。状態によっては、妊娠末期まで子宮の入り口を糸で縫って頚管縫縮術を行い、早産を予防することもあります。
膣や子宮の感染症を起こしている
膣の細菌が上行して子宮が感染することで、赤ちゃんを包む卵膜が感染する「絨毛膜羊膜炎」になることがあります。絨毛膜羊膜炎は、子宮収縮を頻回に起こしやすくなったり、破水しやすくなったりすることで、早産を引き起こす可能性があります。
実は、早産の半数近くが、絨毛膜羊膜炎によるものだと言われています。もともと膣には常在菌と呼ばれる細菌がいますが、膣には自浄作用があり、炎症を起こさないようになっています。しかし、免疫力が低下していると細菌が増殖することで、感染症を起こしやすくなります。
妊娠糖尿病や妊娠高血圧症候群がある
妊娠糖尿病になると、胎児へブドウ糖を始めとした栄養がたくさん移行します。胎児が大きくなりすぎる「巨大児」や羊水が増えすぎる「羊水過多」を引き起こすことで子宮が張りやすくなり早産につながりやすくなります。糖尿病になると免疫力が低下して、感染症にかかりやすくなるため、子宮や膣の感染症にも注意が必要です。
また、妊娠高血圧症候群の場合、血流が悪くなることで赤ちゃんに酸素や栄養が届きにくくなります。重症化すると、赤ちゃんの状態が悪くなったり、発育不全になったりすることで、妊娠の継続が難しくなり、結果的に早産になるリスクが上がります。
双子以上の多胎妊娠
不妊治療の影響などで多胎妊娠が増えていますが、多胎妊娠の場合、約50%で早産になると言われています。1人の赤ちゃんが成長するのに比べて、2人以上の場合、子宮が大きくなり、お腹が張りやすく、早い段階で子宮の収縮を起こしやすくなります。
また、双子の場合、胎盤の数や胎児が成長する部屋の数によって、栄養供給のバランスが崩れてしまうことや臍の緒が絡まるなどのトラブルが生じやすくなります。その結果、発育不全や心不全などを起こしやすくなり、妊娠を継続するのが難しい状態になるリスクもあります。
早産の兆候や気をつけておきたい症状は?
早産になってしまう前に、その兆候に気づいて病院を受診すれば適切に対処してもらい早産を防ぐことができる場合もあります。ここでは、気をつけたい症状について解説します。
出血やおりものの変化
妊娠すると、ホルモンの変化によって出血しやすくなります。そのため、子宮頸部の内側の皮膚がただれる「子宮膣部びらん」によって少量の出血することがありますが、妊娠には影響しないことがほとんどです。ただし、レバーのような血の固まりや真っ赤な血が多量に出るような場合、強い痛みを伴う場合は、子宮や胎盤のトラブルが原因のこともあります。早産につながる可能性があるため、すぐに病院を受診するようにしましょう。
また、子宮や膣の感染症を起こした場合、おりものの色や臭いが変わることもあります。淋菌に感染すると、おりものが黄色くなり臭いもきつくなります。いつもと違うと思ったら、病院へ相談をしましょう。
お腹の張り
子宮の収縮は赤ちゃんの成長に伴って、正常な状態でも起こり得ることです。不規則にお腹が張ることや、軽い痛みがあっても、しばらく安静にしていれば治まることが多いでしょう。
ただし、頻繁に起こる場合や、痛みが周期的に強くなる、いつもと違うタイミングでお腹が張る場合は注意が必要です。早産につながる子宮収縮である可能性が考えられるため、すぐに病院を受診しましょう。
前期破水
破水とは、赤ちゃんが包まれている卵膜が破れて膣から羊水が流れることを言います。通常破水は、いざ出産を行う際の陣痛が強くなって子宮口が広がる頃に起こりますが、何らかの理由で早期に破水してしまうことがあります。
もともと羊水は無菌ですが、破水が起こることにより無菌状態が保てなくなり、細菌感染を起こす可能性が高くなります。特に子宮口と離れた場所で卵膜が破れる「高位破水」の場合、完全に破水した場合と違い、漏れ出す羊水が少なくちょろちょろと流れ出るため、尿もれと見分けがつきにくくなります。羊水は透明かそれに近い薄い黄色です。無臭かやや生臭く感じることがありますが、尿のようにアンモニア臭はないため、尿もれでないかもしれないと思ったら病院へ相談をしましょう。
早産にならないための過ごし方
早産のリスクが高い方や切迫早産と診断された方は、どのように過ごせば良いか悩むかもしれません。早産になりそうな原因によっても注意することは異なりますが、基本的に無理をせず健康的な生活を送ることが重要です。
切迫早産になっている場合は、絶対安静で入院して過ごすこともあります。しかし、すぐに早産に至るような状態でなければ日常生活を送ることができます。むしろ、運動不足の状態が続くことで妊娠高血圧症候群や妊娠糖尿病になることや、悪化することがあるため、妊娠中でもできる運動を取り入れた方が良いことも多いです。ただし、子宮収縮が起こりやすくなる前屈みの姿勢や、重たい荷物を持つこと、立ちっぱなしの状態で過ごすことは、避けましょう。
もともと、肥満体型である場合や妊娠中に急激に体重が増えた場合は、妊娠糖尿病や妊娠高血圧症候群などの合併症になりやすく、結果的に早産につながりやすくなります。糖質や塩分の取りすぎや食べすぎには注意して、体重を管理しましょう。
また、妊娠中はホルモンバランスの変化や生活の変化によってもストレスを感じやすい状態です。過度にストレスがかかると、血管が収縮や子宮の収縮を引き起こしやすくなります。十分な睡眠をとり、うまくリフレッシュしながらストレスを解消しましょう。
まとめ
早産につながりそうな要因があるときは、赤ちゃんが十分育ってから生まれてくれるか心配になると思います。早産になってしまう原因はいくつかありますが、もともとの病気や妊娠の状態によって避けることができない場合もあります。
もしも気になる症状があったときに、病院に相談するなどすぐに対処できるように早産や妊娠について知識をつけておきましょう。食事や運動についても、妊娠週数や経過、病気などによっても細かい点は異なるため、主治医とよく相談しておくとよいでしょう。妊娠の経過をしっかりと把握してより健康的な生活を送ることが大切です。