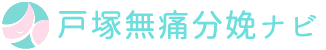Article無痛分娩の適応症|適応外のケースやメリット・デメリットについても解説
コラム 2024.08.30

「無痛分娩はどんな場合にすすめられるの?」「無痛分娩が向かないのはどんなケース?」
分娩時の痛みに対する不安や、無痛分娩を希望したいが誰でも選択可能なのか疑問を持っている人もいるでしょう。基本的に無痛分娩は本人の希望があれば選択可能で、妊娠高血圧症候群や心臓及び脳血管に疾患がある場合は医学的に推奨されるケースもあります。また無痛分娩は硬膜外麻酔下で行われるため、脊柱に疾患がある場合や血液が固まりにくい疾患の方には適しません。
無痛分娩にもメリットとデメリットがあるため、主治医と相談し正しく理解したうえで選択する必要があるでしょう。
無痛分娩とは麻酔によって陣痛を和らげる出産方法
無痛分娩とは麻酔による鎮痛剤を使用しながら、分娩時の痛みを軽減させる出産方法です。
あくまで最低限の痛みを抑える手段のため、全く痛みを感じないわけではなく、出産時の意識も保たれています。無痛分娩時の麻酔方法として選択されるのは、母子への影響が少ないとされる硬膜外麻酔および脊髄くも膜下麻酔です。どちらの方法も脊柱(背骨)から細い針をさし、カテーテルと呼ばれる細い管を挿入後、手術する場所に合わせて麻酔薬を入れます。
出産時の痛みが軽減できるため、体力を温存しながら落ち着いて出産できるのが無痛分娩の利点です。
無痛分娩の適応となる5つのケース
基本的に無痛分娩は本人が希望すれば、選択可能な分娩方法です。なかでも医学的に適応となる状態や疾患は、主に以下の5つです。
1.妊娠高血圧症候群
2.心疾患
3.脳血管疾患
4.精神疾患や出産に対する不安が強いケース
5.微弱陣痛によって分娩が遷延したケース
それぞれの適応理由について解説します。
1.妊娠高血圧症候群
妊娠高血圧症候群とは妊娠時に高血圧を発症した場合をさし、妊娠前から高血圧の方や妊娠20週までに高血圧を認めた場合は、高血圧合併妊娠といいます。妊娠高血圧症候群のリスクには、次のようなものがあります。
・もともと糖尿病、高血圧、腎臓の病気などがある
・肥満
・母体の年齢が40歳以上
・家族に高血圧の人がいる
・双子などの多胎妊娠
・初めてのお産
・以前に妊娠高血圧症候群になったことがある
妊娠高血圧症候群の場合は、分娩中の血圧上昇により脳出血をおこしやすいリスクがあります。また赤ちゃんに十分な酸素が届けられない病態のため、硬膜外麻酔が適していると考えられています。
2.心疾患
心疾患とは、先天的な心臓疾患や不整脈、心臓の機能がうまく働かない心不全などの疾患の総称です。
妊娠すると通常よりも血液量の増加し、脈拍や血圧に変化が生じるため心臓への負担が増加します。無痛分娩の麻酔により血管が緩むため、心臓に戻ってくる血液量をコントロールでき、結果として心臓への負担が減るのです。また分娩時の陣痛によって血管が収縮し心臓への負担が増えるため、痛みを緩和させることも心臓への負担を減らします。
一方で、無痛分娩によって心臓に負担がかかる心疾患があり、例としては大動脈弁狭窄症、閉塞性肥大型心筋症などがあります。よって個々の心疾患の状態に応じた分娩方法の選択が必要です。心疾患の治療として血液が固まりにくくなる薬を服用している場合は、硬膜外麻酔の前に内服薬の調整が必要な場合もあります。
3.脳血管疾患
脳血管疾患とは脳血管のトラブルによっておこる疾患の総称で、脳出血や脳梗塞などが挙げられます。
妊娠前に脳血管疾患のある方もいれば、妊娠に伴う身体の変化(血液の循環量や心拍数の増加、ホルモンの影響など)で、脳血管疾患を発症するケースもあります。
分娩時の陣痛や身体の変化は脳血管に大きな負荷がかかり、出血すれば突然死の可能性や、一命をとりとめたとしても後遺症が残る場合もあります。よって脳血管疾患の状態により、分娩時の陣痛や脳血管への負荷を減らす目的で、無痛分娩が適応されます。
4.精神疾患や出産に対する不安が強いケース
パニック障害や不安神経症などの場合、陣痛への強い不安や痛みに耐えられずパニックになる可能性を考慮し、無痛分娩がすすめられる場合があります。
無痛分娩でも多少は痛みを感じますが、強い痛みや不安は軽減されるでしょう。精神疾患に関わらず、陣痛や出産に対する極度の不安は分娩に影響します。痛みや不安の感じ方は個人差があるため、心配な方は医師へ相談してみましょう。
5.微弱陣痛によって分娩が遷延したケース
微弱陣痛とは、陣痛が通常より弱かったり、間隔が長かったりする状態のことです。
微弱陣痛は分娩が長引いたり、分娩が停止するリスクがあります。分娩が長引くと母体の体力が消耗する原因にもなるため、母体の体力回復を目的に分娩の途中に麻酔が導入されるケースもあります。
無痛分娩が適応されないケース
基本的に無痛分娩は希望すれば選択できますが、無痛分娩で使用する硬膜外麻酔が適さない方がいます。無痛分娩が適応されない主なケースは、次の3つです。
1.血液の凝固機能障害
2.脊柱の問題
3.感染症
それぞれのケースが適応しない理由を解説します。
1.血液の凝固機能障害
硬膜外麻酔の稀な合併症として、硬膜外血腫があります。
硬膜外血腫は、本来、麻酔薬が投与される硬膜外腔に血液のかたまりが溜まり、神経を圧迫する状態です。神経障害が永久的に残る場合があるため、早期の手術を要します。普通の人でも起こる可能性はありますが、特に血液が固まりにくい凝固機能障害のある方は、硬膜外血腫の確率があがるため無痛分娩が適応されません。
2.脊柱の問題
無痛分娩に使用される硬膜外麻酔は、脊柱(背骨)から細いカテーテルを通して麻酔薬を注入する方法です。
脊柱の術後や脊柱に変形がある場合などは、変形の程度・位置によって硬膜外麻酔が難しいため適応されないケースがあります。また脊柱の神経に疾患がある場合も、同様の理由で除外されます。
3.感染症
硬膜外麻酔で麻酔薬を注入する硬膜外腔は無菌の状態です。しかし硬膜外麻酔で脊柱に針をさす皮膚に感染がある場合や、全身の感染症・高熱があるケースでは、硬膜外腔の感染リスクがあるため適応されません。
上記以外にも、麻酔薬のアレルギーや肥満、基礎疾患によっては適さない場合がありますので、無痛分娩を希望される場合は、医師としっかり相談する必要があります。
無痛分娩のメリット
無痛分娩のメリットには、次のようなものがあります。
・陣痛が軽減される
・産後の体力回復が早い
・分娩による母体のリスクが軽減される
分娩時の痛みは感じ方に個人差があり、初産婦か経産婦でも違いがあります。とても強い痛みとして知られているがんの痛みや関節痛よりも、さらに強い痛みを感じるともいわれており、痛みに対して不安を抱える方もいるでしょう。
無痛分娩は全くの無痛ではありませんが、痛みの緩和が最大のメリットです。痛みは心身ともにストレスが大きく体力も消耗するため、痛みの軽減により分娩中の体力が温存され産後の回復も早いといわれています。また無痛分娩が適応される疾患を抱える方にとっては、分娩による母体のリスク回避にもなります。
無痛分娩のデメリット
無痛分娩時のデメリットとリスクは、次のようなものがあります。
・分娩時間が長引くことがある
・吸引や鉗子(かんし)など器具を使用した分娩が増える
・陣痛促進剤の使用が増える
・硬膜外麻酔の合併症がある(頭痛・足のしびれ・感染・硬膜外血種など)
無痛分娩で陣痛が微弱になり、赤ちゃんを押し出す力が弱まった場合には分娩が長引くことがあります。よって赤ちゃんが出てくるのを助けるために、鉗子(かんし)などの器具を使ったり、陣痛促進剤をつかったりする頻度が増えます。また硬膜外麻酔の副作用もデメリットのひとつで、頭痛や足のしびれなど自然に軽快するものから、感染症や硬膜外血種など処置を要する合併症があります。
メリットだけでなく、デメリットやリスクも正しく理解したうえで、無痛分娩を選択する必要があります。
まとめ
無痛分娩は基本的にご本人の希望で選択可能な分娩方法です。
痛みが軽減されるため、分娩中の体力を温存でき落ち着いて出産に望めるメリットがあります。特に医学的な観点から、妊娠高血圧症候群や心疾患・脳血管疾患、パニック障害の方には適応症としてすすめられるケースがあります。
一方、血液の凝固障害があったり脊柱に問題を抱えたりする方は無痛分娩が推奨されないケースです。麻酔を使用するため陣痛が微弱になり分娩が長引いたり、硬膜外麻酔の合併症も考慮する必要があります。
ご自身の状態とメリット・デメリットについてしっかり医師とも相談して選択しましょう。